目次
お年玉制度
正月が来るとともに、もれなくついてくるこのイベント、大人が子供に現金を手渡すという生々しい行為が正当化されるイベントとして受け継がれているものである。
この制度、もらう側だった子供の頃はとてつもなく素敵なイベントだが、与える側になった途端、ハイリスク、ノーリターンのイベントに成り下がる。
お年玉をあげる側になった際の考え方
お年玉=ハイリスク、ハイリターンなイベントを乗り越えるには「恩送り」というパラダイムシフトを行う必要がある。
「恩送り」とは、今までお年玉をくれた人たちに向け、恩返しはできないが、その恩を小さな子供たちに送るという考え。
この思考ができるようになれば、年に1回、正月にしか顔を出さない親戚の子供たちにだって、笑顔で現金を渡すことができるようになる。
子供たちが小さい頃はこの考え方である程度納得できるのだが、子供が成長した時が問題となる。
問題は「辞め時」
物事には、始まりと終わりがあるもので、辞め時は重要である。

お年玉を辞めるタイミング(方法)として、私が考えるのは以下の5つ
※(ジャッジグレー)とあるのは微妙な現場判定があることを示す・
- そもそも正月に遊びにこない。
- 社会人として自立した(ジャッジグレー)
- 結婚して子供が生まれるなど大人の仲間入りをした(ジャッジグレー)
- 25歳をすぎた(ジャッジグレー)
- 正月に家にいないようにする。
この中で明確なのは1と5だけであるが、そもそも今回の「辞め時」とは意味が違うし、5にいたっては自分の人間の器の小ささが逆に苦しくなる。
言ってみれば、お年玉を与えていた対象が「大人」なのか「子供」なのかが、決めてとなるわけである。
ここで一番の問題が「大人判定の曖昧さ」である。
何をもって大人なのか
順を追ってみてみよう。
1.そもそも正月に遊びにこない。
これ以上お年玉を上げない理由はないほど明確、逆に大人都合でお年玉を貰える権利すら無くなる子供が可哀想ともいえる。
2.社会人として自立した。
ふむふむ、自分で働き、お給料をもらえるようになった時点で、無条件にお正月という理由だけで現金を貰えるという夢のイベントは終わりを告げても良いとは思う。
しかし、これが高卒で就職してまだ十代だったらどうだろう?
大学に進学すると卒業するまでは学生となる。「学生」=「子供」という構図が当てはまり、22歳まではお年玉をあげる対象となると考えると、就職したからと言って十代でお年玉を上げないのは可哀想である。
逆に、十代で稼いでいる頑張りを考えれば、お年玉を与えるべき対象であると考える。
結論:状況によっては率先してあげるべき(^_^;)
3.結婚して子供が生まれるなど大人の仲間入りをした
これは解り易い、子供が産まれ親となった時点で強制的に「もらう側」から「与える側」になる。
今回はあくまで「お年玉」に限った考察となるので、結婚時や出産時などのお祝いは含めない。
しかし、産まれた子供は「お年玉」対象となるので、結局何も変わらないという事実がある。
結論:大人になったらなったで、その他でのお祝いが増える。
4.25歳を過ぎた
25歳過ぎたら、もういいでしょ。たとえ大学院に上がったとしても、浪人だったとしても、働いてなかったとしても、もう勘弁してくださいよ。特に親戚の子供
結論:25歳にて、お年玉権利はく奪でいいような気がする。
5.正月に家にいないようにする。
そもそも、お年玉を上げたくないという理由で外出するぐらいであれば、居留守使った方が潔い。
問題は、お年玉を辞める時期であり、あげなくてもよい方法を考えているわけではない。
まとめ
結論としては、その子供の状況によりジャッジが変わるという事実
問題は、姪っ子が、学生なのに、キャバクラでバイトして、自分より収入が多いと思われる場合。
伯父というプライドと、いくら包むかという葛藤で逃げ出したくなる。
というか、こんなことを考えている時点で情けない自分に今気が付いた(T□T)





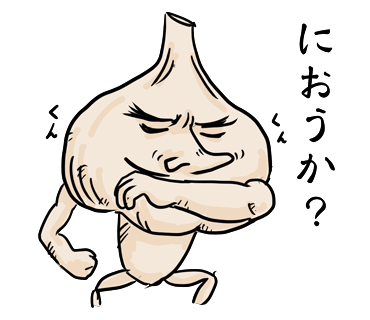


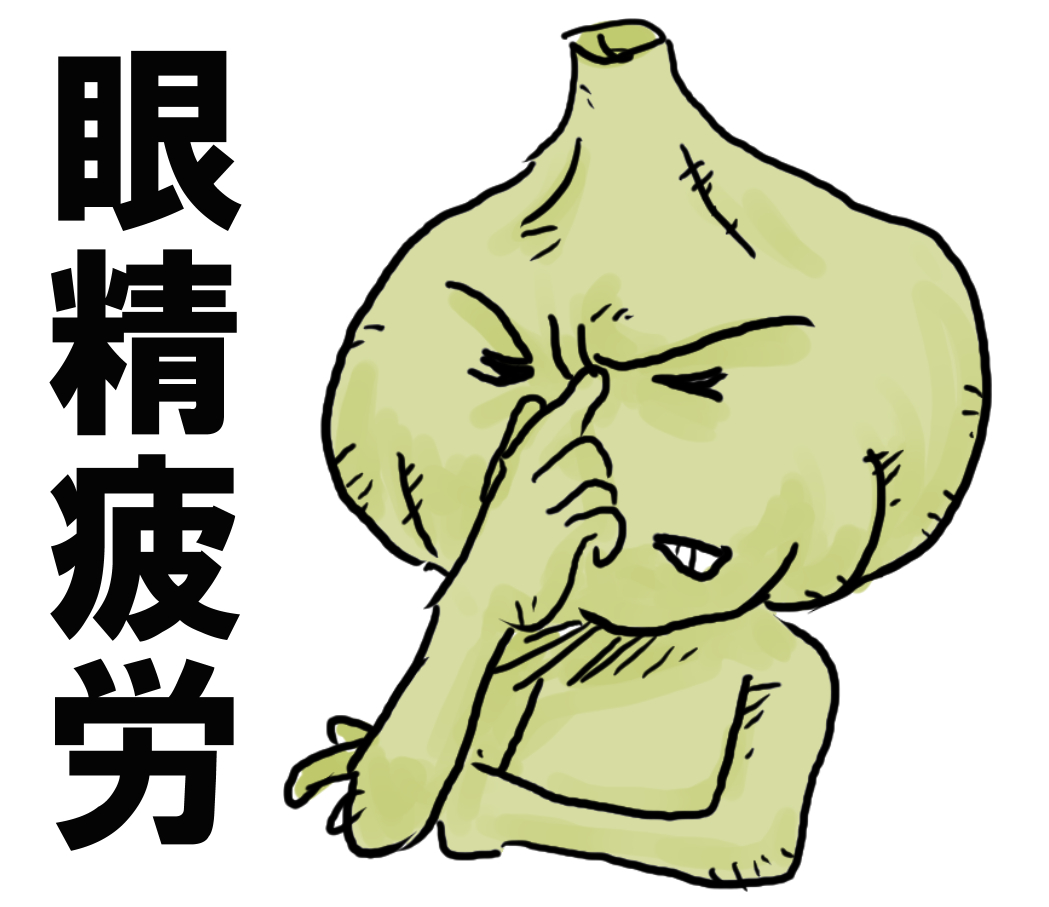



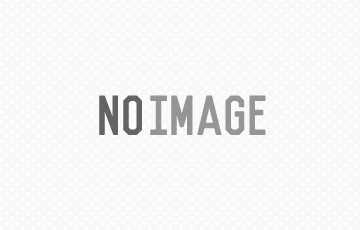



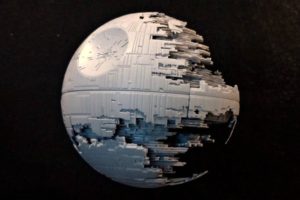











コメントを残す